インディーゲームはどの国で作られているか
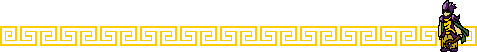
これまでNintendo Switchのゲームを多数レビューしてきましたが、今回はその内容をまとめて、全体的な傾向性などをつかんでみたいと思います。まずはインディーゲームが制作された国を見てみましょう。果たして現在、どんな国でゲームが作られているのでしょうか。
インディーゲームの制作状況の分析を通して、昨今のゲーム業界の展望についても考えてみます。
インディーゲームの制作状況
時は今、インディーゲーム戦国時代である。アンダーテール、ホロウナイト、セレステ、Baba is Youなど話題となるゲームが次々と小規模なデベロッパーあるいは個人の手により生まれている。その数は大規模なスタッフを抱えるゲームメーカーを上回るほどであるし、質についてもそうしたメーカーの大作と比べても(3Dなどの技術以外は)遜色ない。
これはある意味、時代に逆行することかもしれない。ドラクエ1やFF1は実際数人規模のチームで作られていたわけであり、そこから今のような巨大メーカーに成長したわけであるが、そのゲーム黎明期に似た開発規模でさまざまなゲームが制作されているのだ。
実際、インディーゲームの制作は、個人または数人のチームが多大な時間をかけて作り上げるケースがほとんどである。たとえばバットバリアンは4年、フェノトピアは6年、アイコノクラスツは7年もかかっている。さらに制作チームが小規模なゆえに、1人が何役もこなしているケースも多い。洞窟物語の天谷氏は5年以上かけて本作のプログラム、グラフィック、ストーリーを作り上げ、独自のサウンドドライバまで開発している。さらにアンダーテールのトビー・フォックスもよく知られているが、彼もまたほぼ独力であの傑作を制作したのだ。
当サイトは、そんなインディーゲームを中心に、「Nintendo Switchダウンロードソフト おすすめ作品一覧」として多数の作品を紹介してきた。現在その数は70以上となったので、ここでその記録から、インディーゲーム制作の現状を把握することを試みてみたい。
インディーゲームの制作された国
まず着目したいのが、インディーゲームの産地である。現在では、特にPCゲームではいろんな国のゲームに触れることができるようになったが、どこがたくさんのゲームを作っているのだろうか。そして国や地域ごとの特色は見られるのか。
そうした疑問に答えるべく、レビューしたソフトが制作された国を調べてみた。デベロッパーの所在地を基準ととしてそれぞれ調査したが、ネット上にも情報がないものはスタッフロールの人名から判断したり、言語設定から推測したりしたものもある(韓国語に対応しているのに翻訳スタッフがいないのでネイティブだな、とか)。
今回はSwitchの日本語化されているゲームのみを対象としているので、どうしても偏りは出てくる。本当に公平に調べたいならSteamの英語版ゲームも含めて考えるべきだろうが、おすすめゲーム紹介のついでということもあるし、Switchだけでもそれなりに有意義な情報が提供できるのではないかと思う。
各作品の制作された国一覧は次のようになる。
| タイトル | 国 | 地域 |
|---|---|---|
| Hollow Knight | オーストラリア | 西ヨーロッパ |
| フェノトピア | アメリカ | 北米 |
| Cross Code | ドイツ | 西ヨーロッパ |
| バットバリアン | アメリカ | 北米 |
| Celeste | カナダ | 北米 |
| Super Meat Boy | アメリカ | 北米 |
| LA-MULANA | 日本 | 日本 |
| Iconoclasts | スウェーデン | 北欧 |
| Rogue Heroes: テイソスの遺跡 | アメリカ | 北米 |
| Good Job! | オランダ | 西ヨーロッパ |
| オーバークック | イギリス | 西ヨーロッパ |
| カニノケンカ -Fight Crab- | 日本 | 日本 |
| River City Girls | アメリカ | 北米 |
| シドニー・ハンターとマヤの呪い | カナダ | 北米 |
| スメルター | 日本 | 日本 |
| ムーンライター | スペイン | 南ヨーロッパ |
| アリエッタ・オブ・スピリッツ | フィンランド | 北欧 |
| 迷宮伝説 | 日本 | 日本 |
| Gunlord X | ドイツ | 西ヨーロッパ |
| WILD GUNS Reloaded | 日本 | 日本 |
| ゴブリンソード | ギリシャ | 南ヨーロッパ |
| Bug Fables | パナマ | 中南米 |
| UNDERTALE | アメリカ | 北米 |
| Slay the Spire | アメリカ | 北米 |
| Banners of Ruin | イギリス | 西ヨーロッパ |
| 片道勇者プラス | 日本 | 日本 |
| Kingdom Rush Frontiers | ウルグアイ | 中南米 |
| Defend the Rook | オーストラリア | 西ヨーロッパ |
| ダンジョン・ウォーフェア | 韓国 | 中韓 |
| Graveyard Keeper | ロシア | 東欧 |
| Deadly Days | ドイツ | 西ヨーロッパ |
| タウンズメン | ドイツ | 西ヨーロッパ |
| VA-11 Hall-A ヴァルハラ | ベネズエラ | 中南米 |
| メガクアリウム | イギリス | 西ヨーロッパ |
| デプス・オブ・エキスティンクション | アメリカ | 北米 |
| Kingdom: New Lands | オランダ | 西ヨーロッパ |
| Baba Is You | フィンランド | 北欧 |
| ヒューマン・リソース・マシーン | アメリカ | 北米 |
| セブン・ビリオン・ヒューマンズ | アメリカ | 北米 |
| オートマシェフ | デンマーク | 北欧 |
| Old School Musical | フランス | 南ヨーロッパ |
| Dead Cells | フランス | 南ヨーロッパ |
| Enter the Gungeon | アメリカ | 北米 |
| Exit the Gungeon | アメリカ | 北米 |
| クリプト・オブ・ネクロダンサー | カナダ | 北米 |
| ケイデンス・オブ・ハイラル | カナダ | 北米 |
| Spelunky | アメリカ | 北米 |
| HADES | アメリカ | 北米 |
| Caveblazers | イギリス | 西ヨーロッパ |
| ダングリード | 韓国 | 中韓 |
| Wizard of Legend | 韓国 | 中韓 |
| Neon Abyss | 中国 | 中韓 |
| Metaverse Keeper | 中国 | 中韓 |
| マナスパーク | ブラジル | 中南米 |
| クリタデル | 韓国 | 中韓 |
| ゼノン ヴァルキリー | スペイン | 南ヨーロッパ |
| Demon's Tier+ | スペイン | 南ヨーロッパ |
| ソード・オブ・ザ・ネクロマンサー | スペイン | 南ヨーロッパ |
| ライジングヘル | インドネシア | 東南アジア |
| Rush Rover | 中国 | 中韓 |
| Momodora:月下のレクイエム | ブラジル | 中南米 |
| ゴッド・オブ・ウォール | 日本 | 日本 |
| Throne Quest Deluxe | イギリス | 西ヨーロッパ |
| ロック・オブ・エイジス | チリ | 中南米 |
| RPGolf Legends | イタリア | 南ヨーロッパ |
| ジェット・セット・ナイツ | スペイン | 南ヨーロッパ |
| リドルドコープスEX | スペイン | 南ヨーロッパ |
| カルマナイト | 韓国 | 中韓 |
| DUNGEON RUSHERS | フランス | 南ヨーロッパ |
| Legend of Keepers | フランス | 南ヨーロッパ |
| ルーンストーン・キーパー | 中国 | 中韓 |
| World for Two | 日本 | 日本 |
| 大繁盛!まんぷくマルシェ | 日本 | 日本 |
| 迷宮経営SLG -ZombieVital DG- | 日本 | 日本 |
このリストを、まずは国単位で集計してみよう。上位はこのようになる。
| 国名 | 本数 |
|---|---|
| アメリカ | 14 |
| 日本 | 10 |
| スペイン | 6 |
| イギリス | 5 |
| 韓国 | 5 |
| カナダ | 4 |
| ドイツ | 4 |
| フランス | 4 |
| 中国 | 4 |
まあ大きい国が目立っているという感じだろうか。もう少しわかりやすくするために、地域でまとめてみよう。上のリストに記載したが、「西ヨーロッパ」は主にゲルマン語圏(オーストラリア含む)、「南ヨーロッパ」は主にラテン語圏で区分している。
| 地域名 | 本数 |
|---|---|
| 北米 | 18 |
| 西ヨーロッパ | 13 |
| 南ヨーロッパ | 12 |
| 日本 | 10 |
| 中韓 | 9 |
| 中南米 | 6 |
| 北欧 | 4 |
| 東欧 | 1 |
| 東南アジア | 1 |
こうしてまとめると、西ヨーロッパと南ヨーロッパが日本を上回る数になり、中南米や南ヨーロッパもそこそこ多いことがわかる。もちろんアメリカは強いが、全体としてゲーム制作の拠点が世界中に広がっていることがわかるだろう。
比較対象として、3DSのおすすめダウンロードソフトの産地もまとめてみよう。
| 地域名 | 本数 |
|---|---|
| 日本 | 35 |
| 西ヨーロッパ | 2 |
| 北米 | 1 |
| 南ヨーロッパ | 1 |
| 北欧 | 1 |
| 東南アジア | 1 |
これらのソフトが発売された時期が2015年前後で、Switchの方は2020年前後と考えてよいが、わずか5年の間に割合がまったく変わってしまっている。これは何より、Switchの時代になって海外のソフトが積極的に翻訳発売されるようになったというのはあるが、それにしても日本のゲームの存在感の薄れっぷりは顕著である。
インディーゲームの国・地域ごとの違い
では、こうしてまとめてみて、国や地域ごとに特色は見つかるだろうか。どうしても大雑把なまとめになるのは仕方ないとしても、ゲームの内容からそうした特色について考えてみよう。
北米
アメリカは現在でも世界の文化の発信地ということもあり、やはり影響力のあるゲームが多い。特にThe Binding of Isaac、Enter the Gungeon、Slay the Spireと1ジャンルを形成し、多数のフォロワーを生むような作品はみんなアメリカ産である。
しかも元となったリストではFPSなどの定番をほぼ入れていないので、そうしたものを含めると数は数倍になるだろう。加えてカナダも、セレステやネクロダンサーなどアメリカに劣らないインパクトがある。
中南米
圧倒的な人気作はないものの、ベネズエラのVA-11 Hall-Aに加えMomodoraシリーズなど継続して作品を送り出している例もあり、Kingdom RushシリーズのIronhideも中南米が拠点だ。
また、Bug Fablesはパナマ産というとても珍しい出自だが、非常にクオリティが高い素晴らしい作品だった。
西ヨーロッパ
総じてアクションが好きな英米に対し、ドイツ・フランスはターンベースのRPGやシミュレーションを結構作っている印象がある。渋い戦略ゲームを多数出しているGoblinz Studioがその例だろう。
CrossCodeはドイツ産のアクションRPGだが、日本のSFC時代のゲームを意識しているところもあり、ストーリーも壮大な大作だった。
南ヨーロッパ
Goblinz Studioのものを除いて、だいたいがアクションである。Dead Cellsはフランスの大傑作だし、スペインもゼノンヴァルキリーのチャベス氏をはじめとして結構頑張っている。
スペインのゲームは助成金を受けたと書いてあるものがあり、公的支援があるのかもしれない。
中韓
韓国はダングリードとWizard of Legendというローグライクアクションの傑作を生み出している。全体的に小規模だがクオリティは高い印象だ。
中国はボリューム主義というか、いろいろな要素が多数盛り込まれたゲームが多い感じ。あまり独創性が見られないのと、翻訳で手を抜きがちなのが欠点。
日本
翻って日本のゲーム制作事情を考えてみると、やはりスマートフォンゲームにリソースが割かれているのか、前述の通り3DS時代から明らかに後退している。しかもよく見るとリストのゲームの多くが「そこそこ編」の方だし、LA-MULANAや片道勇者は元は結構昔の作品である。
ただ、一方でパブリッシングの方は盛んだといえるだろう。これは次回詳しく扱う予定だが、そもそも海外のゲームがたくさん遊べるようになったのも、日本に輸入して販売しているメーカーのおかげである。加えて紹介しきれなかった分としては、ケムコなどはかなり意欲的にゲームを出している。
今回は、インディーゲームの制作された国の情報から、ゲーム業界の現状の理解を試みてみた。昨今では、世界中の人々が(主に西洋文化圏+日中韓ではあるが)ゲーム制作にチャレンジし、時には大きなインパクトを与える作品を生んでいる状況である。
次回もインディーゲーム戦国時代の状況を把握すべく、ゲーム会社に焦点を当てて分析を行ってみたい。
 ゲーム思い出語り ~PCのフリーゲーム~
ゲーム思い出語り ~PCのフリーゲーム~
